皆さんは「販促とは何か」と聞かれたらどう答えますか。キャンペーン、SNS、チラシなどを通じ少しでも売れるようにする、これも一つの答えでしょうが、私はシンプルに「伝えること」だと考えています。特にリアル店舗においては「五感にダイレクトに、ミックスして伝えること」ではないでしょうか。価格(お買得感)、品質、味、食べ方、その商品の魅力を精一杯伝えることこそ「買う」につながる出発点だからです。


この記事は約 - 分で読めます
私は、長きにわたりチラシやカタログ、52週販促計画立案など、小売現場での販促に関わってきました。特に多く手掛けてきたのが「価値伝達型販促」という置いているだけでは価値が伝わらない商品を売る仕事です。また近年は商業誌の誌面で食品小売の話題店を訪ね情報発信をする仕事もしております。それらの経験を生かしたコラムを定期的にお届けすることで、販促に携わる様々な方にエールを送れたらと思ってます。
皆さんは「販促とは何か」と聞かれたらどう答えますか。キャンペーン、SNS、チラシなどを通じ少しでも売れるようにする、これも一つの答えでしょうが、私はシンプルに「伝えること」だと考えています。特にリアル店舗においては「五感にダイレクトに、ミックスして伝えること」ではないでしょうか。価格(お買得感)、品質、味、食べ方、その商品の魅力を精一杯伝えることこそ「買う」につながる出発点だからです。
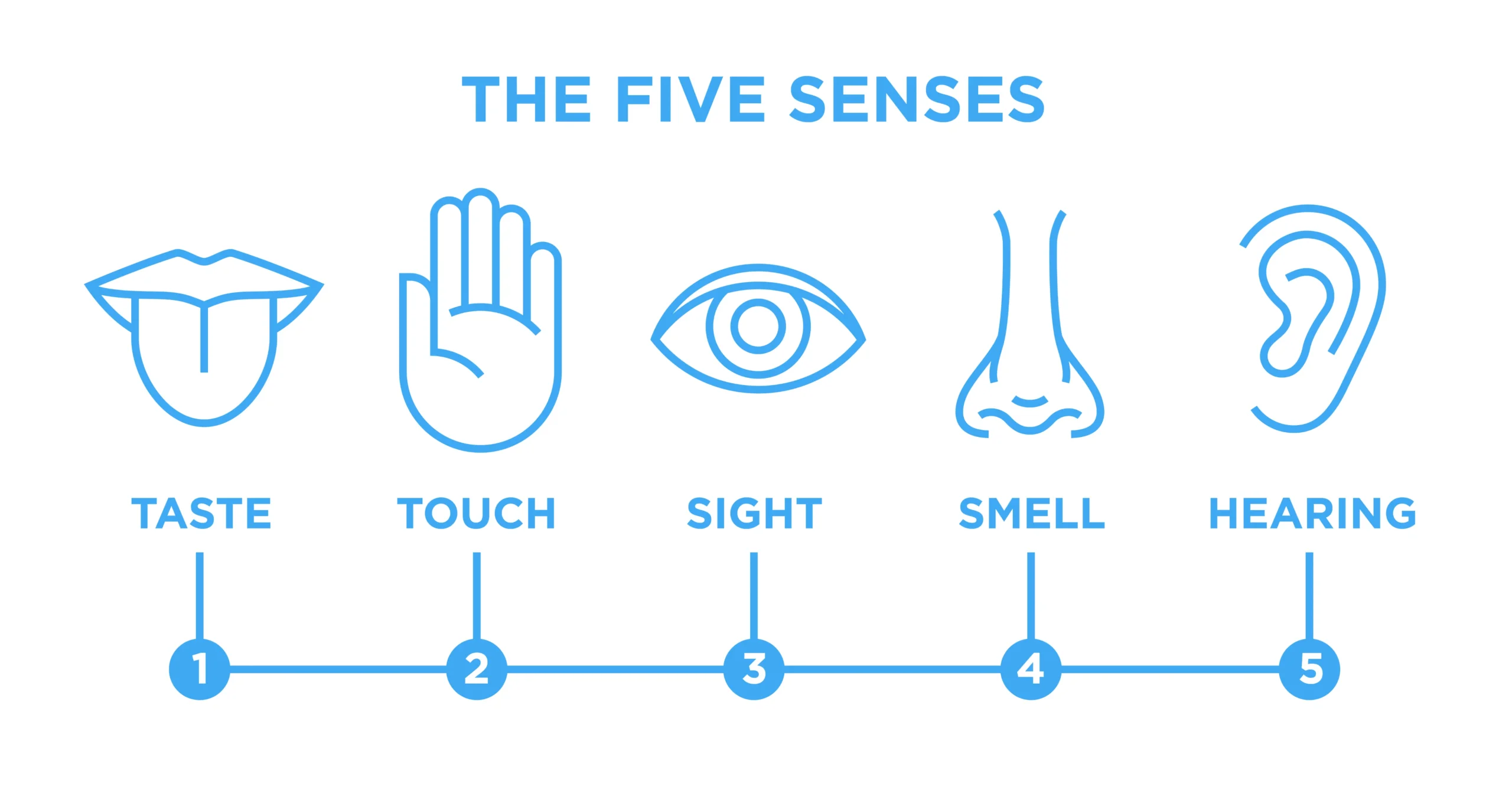
そしてあらゆるものが値上げされている昨今、顧客に「価値の割に安い」と納得していただける伝え方がとても重要です。
どの手法で伝えるにしても、大切なのは「伝える中身=情報を充実させる」こと。そのためには誰よりも社内のあらゆることを「知る」ことです。今の食品小売は他社との差別化、自社の個性を前面に出し「尖ること」が求められています。ゆえに、販促に携わる人には自社方針に基づいた一つひとつの開発商品、売場、とにかくあらゆることを知っていただきたい。
待っていても、情報は歩いてきてくれません。外部情報は取引先やネットからも収集でき、社内情報もそこそこは入ってきますが、本当に踏み込んで「知る」ためには自ら各部門とつながり情報を取りに行くことが必要です。商品は何か月も何年もかけて開発されるわけですから、商品が出来上がった後、情報をメールでもらうくらいでは顧客を納得させるにはさすがに弱い。開発プロセス、開発者の思い、真の魅力を知り、それをいかに顧客に伝え共感、納得を生み出すかが非常に重要です。
知ること=顧客の購買行動を変えられるくらいの情報量を持つこと、これこそが販促のスタートラインです。もちろん販促会社に全て依頼する、これも一つの方法ですが、それならば販促会社のスタッフに「知る」環境を整えておくことが大切です。
販促ツールにはSNS、チラシ、リーフレットなどさまざまな種類がありますが、それぞれのツール特製を理解した上でフル活用する必要があります。one to oneマーケティングとしてのアプリ活用は当然のこと、Instagramやfacebookはファン醸成の場としての役割も大きい。どのツールを使って情報発信するにしても、他社と差別化する為には、販促担当がどれだけ内容の濃い発信情報の中身を組み立てるかに関わってきます。それをベースに個々の販促物ができるわけです。もちろん販促会社は、よりよい販促物を創ることはできますが、どんなに素晴らしい制作スキルを持っていても、情報の中身が薄ければクオリティにも限界があります。
私自身、たとえば「有名メーカーのたれのキャンペーンをするので、御社のブリを使った照り焼きメニューで情報発信したい」といった要望は安易に受けませんでした。本当にそれが自社のブリの良さを伝える最適な食べ方なら喜んで仕掛けますが、ブリ自体の旨みが他社に比べて抜群ならば、塩焼きしゃぶしゃぶといったメニューの方がよいかもしれません。マーチャンダイザーが強い思いを持ち、商品を開発していることを知るからこそ発信する情報もベストなものにしたいと思うわけです。
とはいえあまり難しく考えず、販促担当は顧客目線をもち情報収集に徹し、販促会社のプロとチームで動ける環境を整える、まずはここからでしょう。
次は、知りえた情報をいかにお客様の「買う」につなげるかの話です。
リアル店舗の場合、売上の殆どはレジを通過して成り立ちます。当然ですが、売場でいかに商品をカゴに入れてもらうかが最大ポイントです。そういう意味ではインストアマーチャンダイジングがベースとなります。お客様の購買行動で活躍するのは「五感」=視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚です。五感から知りうる情報量として最も多いのは視覚で、だいたい7割から8割の情報が視覚から得られると言われています。視覚で認知してもらう為にはモノの見え方を知ること。これらは「センス、感性がある」という抽象的なものでなく、科学的なものとし体系づけられています。その知識をつけるため、「ダイヤモンド・チェーンストア・オンライン」掲載の記事にもあるように、小売各社で色彩検定などのスキル取得も進みつつあります。

魅力的な売場…抽象的な誉め言葉の意味を明確化するために必要なこととは _流通・小売業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】
かくいう私も色彩検定1級を取得し、VMDの勉強もしました。五感に関する細かいことは今後お話するとして、買物時、視覚がフル活用されるのは当然のこと、意外と聴覚、嗅覚はフリーで視覚より遠くに伝える力があります。「いらっしゃいませ」の連呼では挨拶どまりですが、「今日は鮭がお買い得だよ」「当社の唐揚げは精肉売場で人気の〇〇鶏を使用しています」というような大切な商品情報は、無意識のうちに顧客にインプットされていることがあります。そして、その情報は「すぐに買う」につながらなくても、後々の購買行動につながることもあるのです。クッキングサポートで声を出しながら毎日商品紹介していると、お客様がいらして「この前紹介していたあの商品、今日買いたいんだけど、どこにありますか?」とか「いい匂いがしたから、何をしてるのか見に来た」というのはよくあることなのです。
最後に、今の小売環境を踏まえた販促のあり方を一つご紹介します。写真はトライアルのオリジナル商品です。トライアルは取引先、生産者の皆様とのモノづくりを進める中、生鮮のオンパックシール、セロファンを上手に販促物として活用しています。この商品は、サンキスト社と商品開発した大玉オレンジ。このような商品開発は各社されていますが、セロファンまで開発するというのはあまり見られせん。

というのもこれらは商品部の副包材であり、販促担当の制作物ではないことが多いからです。販促物としては、POP、ボードなどが一般的です。仮にこの情報をPOPで送るとしましょう。全店に送ればセロファンとは別に制作コストもかかります。セロファンで包む+POPを取り付ける、はトータルで工数2となります。さらにPOP付け忘れ、POPと商品の不一致などの問題も起きます。かといって、このセロファンを各店に送り込み、様々な柑橘がある中で「このオレンジにだけセロファンを使って」というオペレーションは至難の技。
でも、プロセスセンターにパック作業を移管していませんか。それならばセロファンもパック作業も集約されますよね。この商品なら店舗も商品を並べプライスカードをつけるだけ。何より、メーカー・ベンダー側からしたら、小売がこのようなセロファンを作って全ての商品につけてくれると、顧客の食卓まで情報がダイレクトに届く、これはとてもうれしいことなのです。
セロファンの経費をどこにつけるかなどは各社で決めることでしょうが、仕組みが変わればこういうやり方もあるのだよ、という一例としてご紹介させていただきました。
食品スーパーのお客様の8割は買うものを明確に決めずに来店しているとも言われます。食品を買うことは「生きるため、家族を生かすため」に必須、多忙な中で一種の義務感に追われての来店も少なくありません。だからこそ、気づきや楽しさの多い店は選ばれ、再来店につながるのでしょう。